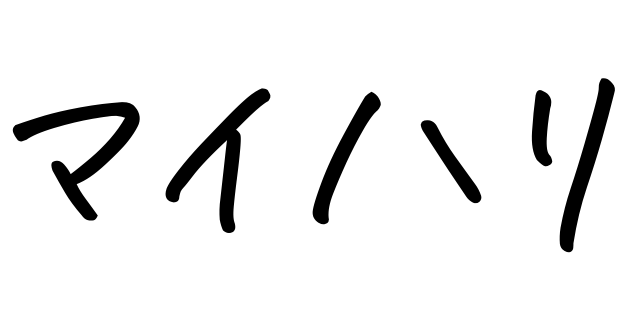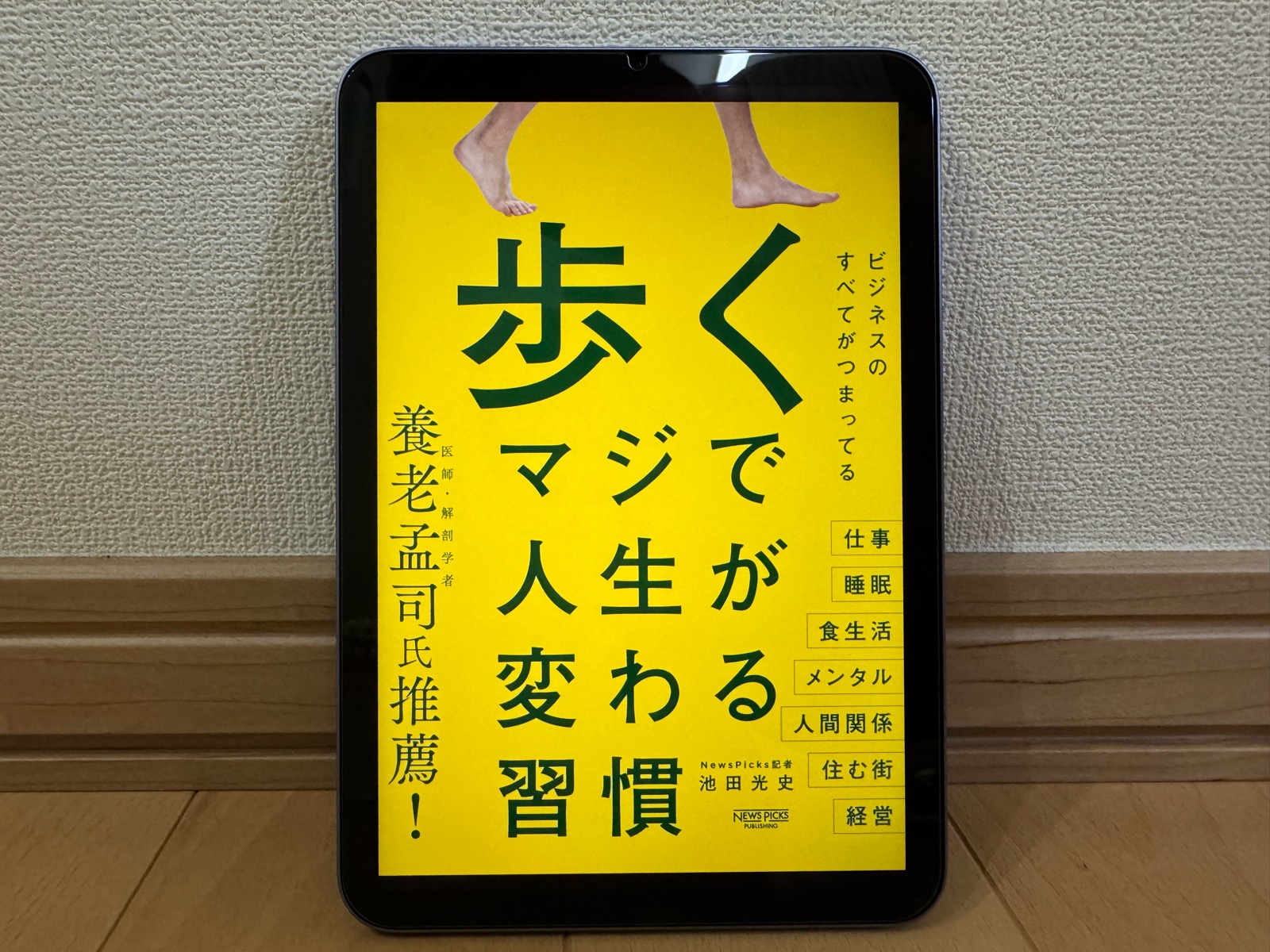『歩く マジで人生が変わる習慣』 池田光史 (著)は、読むともっと歩きたくなる本です。
普段履いている靴についても考えさせられます。
広告
著者について
池田光史
経済ジャーナリスト。
週刊ダイヤモンド編集部にて金融、日銀・財務省、自動車業界を担当。
NewsPicks編集長、CXOを経て現在NewsPicks CMO(Chief Media Officer)。
経済ジャーナリストとして地歩を固めたのち、取材で体験した登山をきっかけに「歩く」ことを探求し始める。
なぜこの本を読もうと思ったのか?
もっと歩く習慣を定着させたいと思っていたので、「歩く」というタイトルの本著が目に留まりました。
また、『BORN TO RUN』を読んでから、ベアフットシューズ(裸足感覚のシューズ)にも興味があり、最近のベアフットシューズの情報も知りたいと思いました。
主な本の内容
歩くことで創造性を高める
「歩くことは、既存の枠にはまらない、発散的な思考力を高めることにこそ効果がある」とのこと。
歩くことを習慣化し、歩きながらアイデアを考えることが、創造性を高めることにつながります。
定期的に自然の中を歩くと、なお効果的だそうです。
『Barefoot Shoes (ベアフット シューズ)』で足本来の機能を取り戻す
『BORN TO RUN』にもありましたが、現代の靴が足に何かしらの悪さをしていると考えられます。
短い歩行距離だとあまり痛みを感じることもなく、長い年月をかけてじわじわと足を変形させているのです。
靴が足(脚)を守るという考え方もありますが、靴が本来の足の機能を阻害していることもあるのです。
つま先が広く、つま先と踵の高低差が小さく、クッションが過剰ではない、ベアフットシューズを履くことで足本来の機能を取り戻すことができます。
歩くのは効率的な運動
ちょっと意外だったのは、歩くのは効率的な運動で、エネルギー消費が小さいということ。
エネルギー消費が大きいと、狩猟や採集で得られるエネルギーでは生きていけなかったから。
なので、歩くだけで劇的に痩せることは無さそうです。
とはいえ、歩くことで血糖値や血圧が下がるなど、いろいろな不具合を減らせることは確認されています。
自動車優先から歩きやすい街へ
自動車の稼働率はわずか5%で、残りはただスペースを占有しているだけ、というのも驚きでした。
自動運転が実用化されれば、自動車の台数と駐車スペースの大幅な削減が可能となり、街づくりの概念も根本から変わりそうです。
「歩きやすい街」の不動産価値が上がっているというのも納得です。
これからやりたいこと
ベアフットシューズで歩く
つま先が広く、つま先と踵の高低差が小さく、ソールが薄いベアフットシューズで歩いてみます。
革靴も素敵ですが、高温多湿の日本には不向きな気がしますし、足が窮屈な感じがします。
1日1万歩前後を目標に歩く
現状は、1日5,000〜7,000歩くらいの日が多いです。
1日1万歩前後を目標に歩きたいと思います。
お茶でも飲んで一休みできる場所を目指すなど、何か目的を持って歩くのか、何となくブラブラ歩くのか、自分に合った歩き方を探してみます。
まとめ
歩くことのメリットは健康面だけでなく、思考力を高めることにも及びます。
日頃から、もっとたくさん歩くことを意識したいと思いました。
また、徐々にベアフットシューズに切り替えていきたいです。
関連記事
他の本関連の記事は下記リンクから。
こちらからは以上です。